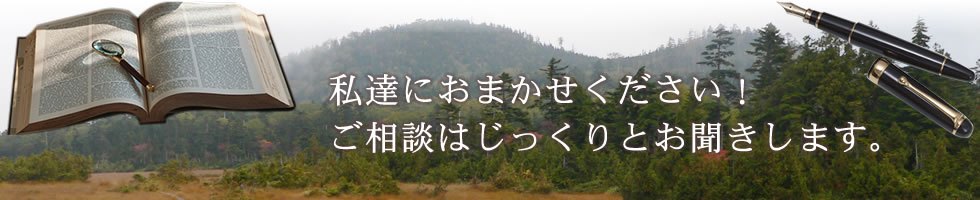1 選択的夫婦別姓制度とは
(1)現行の民法(750条)下では、夫婦は婚姻時、それまで夫または妻が称していた姓のどちらか一方を選んで称さなければなりません(夫婦同姓制度)。統計上、これまで、90%を超える夫婦が婚姻時に夫の姓を選択してきました。
(2)夫だけが外で働き妻は専業主婦があたりまえだった時代にはそれで良かったかもしれません。しかし、男女平等が進み、女性が普通に職業を持ってキャリアを重ね、対外的・社会的に広く活動を行うようになった現代社会で、その女性の大半が結婚後に姓が変わることに伴い、職場や取引先への通知、名刺の刷り直し、学校の同窓会名簿、預貯金通帳、運転免許証、健康保険証、パスポートなどで氏名の表記の変更(旧姓併記を含め)を余儀なくされるというのはやはり大変な不便でしょう。そこに、婚姻前の姓をそのまま使用できる他方側の配偶者と比較しても、両性の本質的平等を謳った憲法14条、24条などに反するのではないかという問題提起がされても不思議ではありません。
(3)そこで、夫婦同姓を定める民法の規定を変え、夫婦同姓でももちろんかまわないが、夫婦のそれぞれが、それまでに称していた姓を結婚後もそのまま称することもできる(戸籍上も変えない)、すなわち夫婦同姓・別姓のいずれも選択ができるという選択的夫婦別姓制度にしよう、そして、関連する戸籍法や家事事件手続法などの法令も必要な限りで改正しようというのが、この制度導入の趣旨なのです。
(4)実は、夫婦別姓制度の提唱は今に始まったことではなく、今から3~40年くらい前にも学者、裁判官、弁護士などの法律実務家の間で検討されましたが、実現に至らなかったので、今再びということなのでしょう。
当時、何故実現しなかったのか、詳しい事情まではわかりませんが、今の選択的夫婦別姓の提唱への反対意見と共通する認識が保守派の人たちの中に(今よりももっと)根強かったことと、戸籍法、家事審判法・規則など関連法令の改正、隅々までの戸籍など諸実務の変更と関係職員の徹底周知(研修など)が複雑で大変だとの認識からではなかったかと思われます。後者の課題には今回も直面することになります。
2 選択的夫婦別姓制度導入反対派の意見とその検討
(1)主に反対派の人たちから主張されているのは、夫婦同姓によってこそ家族の絆・一体性が保てる、夫婦同姓は名字が許されなかったとされる庶民を含めて古来から事実上存続してきた日本の伝統的な制度である、戸籍上は夫婦同姓のままでも旧姓の事実上の使用枠を拡げることで十分な対処ができる、等々のようです。
(2)ここですべての主張を網羅して逐一反論することはできませんが、(1)の主立った主張ははたしてどこまで説得力があるのでしょうか。
まず、夫婦同姓であってこそ家族の絆・一体性が保てるという主張ですが、夫婦同姓は国際的にはかなりマイナーな制度だといわれており、大半を占めると思われる夫婦別姓あるいは姓のない国・民族において家族の絆・一体性がないのかといえば決してそんなことはありません。夫婦同姓のわが国でも同姓でありながら夫婦関係が完全に破綻し、また崩壊してしまった家族は多々あります。
仮に、夫婦同姓が古来から続いてきた日本の伝統的な制度だとしても、それを変えるべき必要性が認められれば変えることは可能であり、伝統イコール不変という公式が世の中に存在する訳ではありません。
法律を変えなくても社会の中で旧姓の事実上の使用枠を拡げることで十分な対処ができるからこの制度の法的な導入までは要らないという最後の論拠ですが、そうなのでしょうか。
先ほども少し触れましたが、職場内や取引先との関係では、相手方の理解も必要ですが、殆どの場合旧姓をそのまま使用できると思われます。名刺の刷り直しも要らないだろうと思います。学校の同窓会名簿も旧姓のままでいいでしょう。しかし、預貯金通帳、運転免許証、健康保険証、パスポートなどは、戸籍と連動する住民票の記載に従うことになるので、原則は戸籍上の姓すなわち婚姻姓で表記されますが、最近では旧姓の併記ができるようになっています(あくまで「併記」でしか認められないということです)。
3 選択的夫婦別姓制度を導入すべきなのか(賛成派の意見をふまえ)
(1)2で検討したところでは、反対派の論拠はあまり説得力を持たないようにも思えます。では、即導入というべきなのでしょうか。
(2)視点の方向を変え、統計すなわち内閣府が実施した世論調査結果(令和4年3月)を少しみて検討したいと思います。
① 現行の夫婦同姓制度の中で、婚姻によって姓を変えた側がはたして不便、不利益を受けてきたかどうかにつき、何らかの不便、不利益ありと答えたのは、男性48.3%、女性55.5%、全体で52.1%でした。不利益の内容について、姓を変更した側のみに変更の負担があるなど日常生活上の不便、不利益はあると答えた方が全体の83.1%を占めていました。
以上を年代別にみていくと、ほぼ40~50歳を境に、それより若年層に、何らかの不便、不利益を受けたと答えた方の割合がかなり多くなり、男女ともに概ね65%~70%を超えています。
② 旧姓を通称として使用することによって不便、不利益は解消されたかどうかにつき、それでも対処しきれない不便、不利益があると答えたのは、男性56.2%、女性61.8%、全体で59.3%でした。これを年代別にみていくと、男性はほぼ50%~64%で年代間に特に大きな差はありませんが、女性の60代以下はほぼ65%~73%といずれも高い割合を示しています。
③ 統計上、50%以上の方が夫婦同姓制度下で婚姻によって姓を変えた側に不便、不利益があったと認識し、また、約60%の人が旧姓を通称として使用することによっても不便、不利益は解消されなかったと認識していたことがわかりました。
④ 但し、この統計結果が令和4年3月のもので、それから3年以上経った現在はどのように変わっているのか、また統計の対象人数が3千人前後と少ないことから国内全体でも同じ傾向にあるのかどうか、若干の疑問が残るところではあります。
(3)選択的夫婦別姓制度の導入に積極的なのは、政党では立憲民主党、共産党などの左派政党だといわれています。ちなみに我が日本弁護士連合会も導入に積極的です。政治的な議論や政党の好き嫌いはさておいて、積極派が主だって主張するのは、1(2)(3)で述べたところです(繰り返しません)。前記のとおり、導入消極派(保守派)が掲げる根拠にはあまり説得力が感じられません。そして、統計上の結果(前記)をみても、実際の世の中の動きがどうなのかはさておいても、理屈の上では、どうも導入積極派に軍配が上がりそうな気配です。
(4)残る課題は、やはり関連法令(戸籍法、家事事件手続法・同規則など)の改正、戸籍実務と関係職員への研修など膨大な実務上の課題の解消でしょうか。
(5)さらには、出生した子の姓の決め方をどう定めるのでしょうか。夫もしくは妻の氏に統一するのでしょうか、夫婦の協議でその都度決めるのでしょうか、もし協議が整わなかった場合にどうなるのでしょうか(多分、家裁の審判で決めるのでしょうが、決め手があるのでしょうか)、夫婦が離婚する場合、親権者と子の氏とが異なる場合も増えるでしょうからそれだけ子の氏の変更審判を使うケースも増えるのではないか等々、検討すべき付随的な課題も多そうです。
(6)ここでは結論を留保しますが、もし選択的夫婦別姓制度を法的に導入するとしても、関連する法令の改正など細かい付随的な論点、課題を逐一拾い上げて検討し、それぞれきちんとした結論を出さなければならず、一筋縄ではいかない大変難しい選択になると思います。