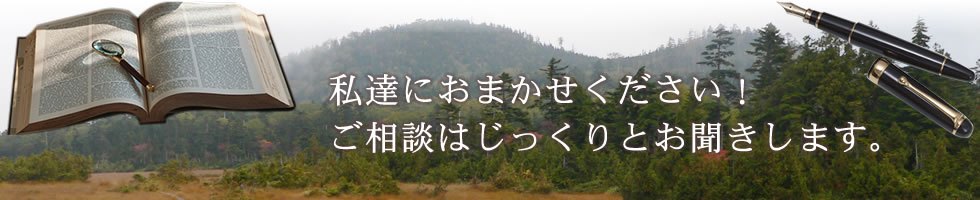1 いつから
令和6年5月17日、民法の一部改正法が成立し(同年5月24日公布)、公布から2年後の令和8年5月24日までに施行すなわち制度が開始されます。以下、改正の内容をみていきます。
2 改正前の民法(819条1~6項)
父母が離婚するときは、その一方を子の親権者と定めなければならない(同条1項)とされていました。単独親権だけでした。
昨今、子の福祉をより尊重する立場から、両親が離婚するのは自由だけれども、離婚後もできる限り両親が従前どおり共同で子に関わっていく方が望ましいとし、離婚後の共同親権の導入が検討されてきましたが、いよいよ実現の運びとなりました。
なお、「原則的に共同親権になる」という報道が一部ありましたが、それは正確ではなく、改正法の819条7項を読む限り、共同親権とすることが困難であると認められるとき、子の心身や利益に害悪を及ぼすおそれがあるときは必ず単独親権としなければなりません。そして、結婚生活が破綻しお互いの信頼を失った父母の多くは今後できるだけ相手と関わりたくないと考えるでしょうから、離婚後の共同親権を拒むケースが大半を占めることになると想像できます。そういった父母に共同親権を押しつけることが理論上直ちに子の心身や利益に害悪を及ぼすとまでは言い切れないけれども、実際こういったケースではなかなか共同親権の実現は難しいともいえ、そうすると、共同親権になるのは父母の双方がいわゆる大人、理性的で、自分たちのわだかまりを捨てて子の福祉のために協力する姿勢を示すことができる少ないケースだけに限られるような気がします(どちらが原則または例外かは言えませんが)。
3 改正後の民法(819条1~7項)
(1)旧法下では父または母の単独親権だけでしたが、当事者の協議により、また、家庭裁判所が、子の利益のため、父母や父母と子との関係など一切の事情を考慮して共同親権と決めることができるようになりました。
(2)但し、父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき、父母が共同して親権を行うことが困難であるときなど、共同親権とすることによって子の利益を害すると認められる場合は、必ず単独親権としなければなりません(同条7項)。
この規定の仕方からすると、2の後段で述べたことが言えそうだということなのです。
(3)婚姻外で出生した子を父が認知した場合、旧法では、原則は母が親権者で、父母間の協議で父を親権者とすることもできる(819条4項)とされていましたが、改正法下では、さらに父母の協議で共同親権にすることも可能になりました。
4 協議離婚届出の際の改正点
今までは共同親権についての法改正に言及しましたが、もう一点、統計的に一番多い協議離婚(夫婦が協議離婚届出用紙に所定事項を記入して市町村役場の窓口に提出するだけで離婚できる場合)の場合、旧法下では、離婚届出の際に子の親権者(単独親権)が指定、記入されていなければ受理されませんでした(765条1項、819条1項)。
しかし、改正法では、離婚届出の際、まだ子の親権について父母間の協議ができていなくても(空欄)、親権者の指定を求める調停または審判の申立がされていれば離婚の届出が受理されることとなりました(765条1項2号)。その場合、家庭裁判所の申立の受理証明書、期日の呼出状などを戸籍役場の窓口に示すことになるのでしょう。
5 離婚後における親権者変更での注意点
次に、離婚時に指定された親権者を後に変更する場合の法改正についてみていきましょう。
(1)旧法下ではすべて単独親権ですから、子の利益の観点から親権者を変更すべき状況があると認められるときは、子の親族の請求と家庭裁判所での審判によって、子の親権者を他の一方に変更することができました(819条6項)。
(2)この旧819条6項とその解釈は改正法下でもほぼそのまま残り、裁判所で決められた親権者を変更する場合に適用されます。
(3)改正法下で、父母の協議で決めた単独親権または共同親権の場合は819条6項ではなく、同条8項を適用し、家庭裁判所において、協議の際に基礎とされた事情にその後重要な変更が生じているか、親権者を変更すべき客観的な事情があるかどうかを考慮し、審判で変更の要否を決めることとなります。
(4)そしてまた、改正法819条7項の必要的単独親権事由がある場合、共同親権にはできず、単独親権としなければなりません。
6 共同親権とした場合の問題点
(1)旧法の単独親権制度の下でも、多くの離婚調停、訴訟において、親権者の指定をめぐり熾烈な争いが繰り返されてきました。
現実的には、父母のうちどちらが子を引き取って起居を共にし養育するかの観点で親権者を決めるケースが多いと思われます。
(2)他方、厳密な意味での「親権」を行使する場面というのはそんなに多くある訳ではなく、例えば、子の進学、退学の際の同意書面への署名・押印、子が15歳未満の場合において父母のいずれかが再婚する場合の新配偶者との代諾養子縁組くらいでしょうか(子の入院のケースだとあまり争いにはならないでしょう)。
(3)一度は子の福祉を考えて理性的に共同親権に同意した一方親も、子の教育方針、進学校の選定や退学となると異議を唱えたり、ましてや自分と血の繋がった子がアカの他人しかも元配偶者の新配偶者の養子となることに反感を抱いてしまうことはありうる話です。
(4)こうした場合、家庭裁判所に、反対する他方親に対して同意を求め、あるいは親権者変更を求めて調停、審判の申立をするのか、それとも弁護士会の窓口でADR(紛争解決のための仲裁、あっせん制度)を申し込んで解決するのか、時間とのたたかいもあり、難しい選択となりそうです。